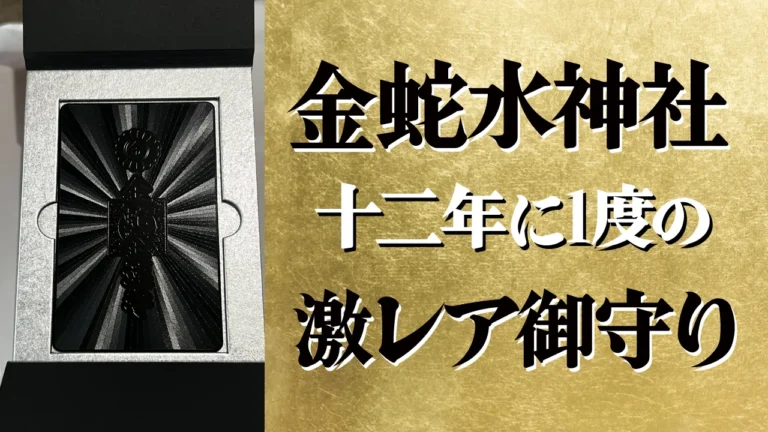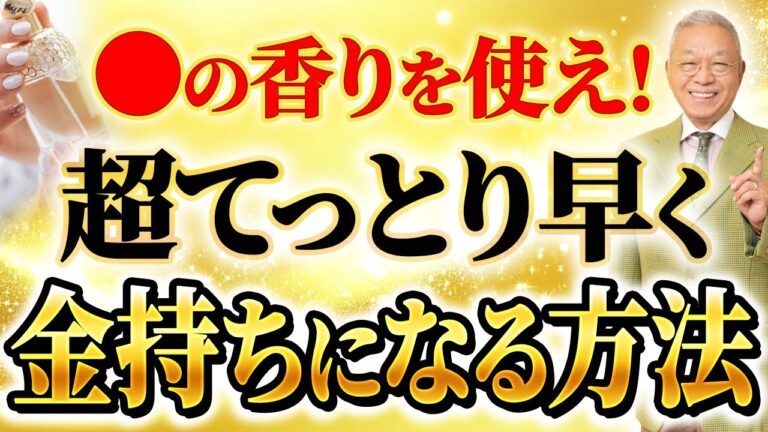「茅の輪くぐり(ちのわくぐり)」は、日本の神道における伝統的な厄除け儀式の一つで、主に6月と12月の「大祓(おおはらえ)」の際に行われます。茅(ちがや)という植物で作られた大きな輪をくぐることで心身を清め、無病息災を願う行事です。
この儀式の起源はスサノオノミコト(素戔嗚尊)にまつわる伝承にあります。あるとき、旅の途中のスサノオが一夜の宿を求めたところ、蘇民将来(そみんしょうらい)という男が、貧しいながらも厚くもてなし、後にスサノオは感謝の印として「茅の輪を腰につけていれば疫病を避けられる」と教え、難を逃れたと伝えられています。
年月が経つにつれて茅の輪は大きくなり、人々はそれをくぐることで災厄を避けようとするようになりました。
茅の輪くぐりは全国の多くの神社で6月30日前後の「夏越の大祓」や、12月の年越しに行われる「年越しの大祓」と呼ばれます。
6月に行われる夏越の大祓は上半期の穢れを祓い、後半も疫病や災害を無事に乗り切ることを願う行事。
この儀式の起源はスサノオノミコト(素戔嗚尊)にまつわる伝承にあります。あるとき、旅の途中のスサノオが一夜の宿を求めたところ、蘇民将来(そみんしょうらい)という男が、貧しいながらも厚くもてなし、後にスサノオは感謝の印として「茅の輪を腰につけていれば疫病を避けられる」と教え、難を逃れたと伝えられています。
年月が経つにつれて茅の輪は大きくなり、人々はそれをくぐることで災厄を避けようとするようになりました。
茅の輪くぐりは全国の多くの神社で6月30日前後の「夏越の大祓」や、12月の年越しに行われる「年越しの大祓」と呼ばれます。
6月に行われる夏越の大祓は上半期の穢れを祓い、後半も疫病や災害を無事に乗り切ることを願う行事。
茅の輪のくぐり方は?

そんな茅の輪ですが「どうやってくぐるの……?」と悩んだ経験はありませんか? 作法としては………。
1. まず左足で茅の輪をまたいでくぐり、左回りに1周して正面に戻り、一礼。
2. 次に右足で茅の輪をまたいでくぐり、右回りに1周して正面に戻り、一礼。
3. もう一度、左足で茅の輪をまたいでくぐり、左回りに1周して正面に戻り、一礼。
4. 最後に、茅の輪をくぐって拝殿しお参りを行う。
くぐるときは、「唱え言葉」を唱えることもあります。
また、夏越の大祓では人形(ひとがた)に自分の名前と年齢を書き、息を吹きかけて神社に納める習慣がある場所も。
茅の輪くぐりは、古来より日本人が自然とともに生き、年中行事を通じて心身の清浄を保ってきたことを象徴する風習です。今年の夏越の大祓では「茅の輪くぐり」に参加してみてはいかがでしょうか♪
こちらの動画では茅の輪のくぐり方を動画で説明! 気になった人はチェックしてみてくださいね。
1. まず左足で茅の輪をまたいでくぐり、左回りに1周して正面に戻り、一礼。
2. 次に右足で茅の輪をまたいでくぐり、右回りに1周して正面に戻り、一礼。
3. もう一度、左足で茅の輪をまたいでくぐり、左回りに1周して正面に戻り、一礼。
4. 最後に、茅の輪をくぐって拝殿しお参りを行う。
くぐるときは、「唱え言葉」を唱えることもあります。
また、夏越の大祓では人形(ひとがた)に自分の名前と年齢を書き、息を吹きかけて神社に納める習慣がある場所も。
茅の輪くぐりは、古来より日本人が自然とともに生き、年中行事を通じて心身の清浄を保ってきたことを象徴する風習です。今年の夏越の大祓では「茅の輪くぐり」に参加してみてはいかがでしょうか♪
こちらの動画では茅の輪のくぐり方を動画で説明! 気になった人はチェックしてみてくださいね。