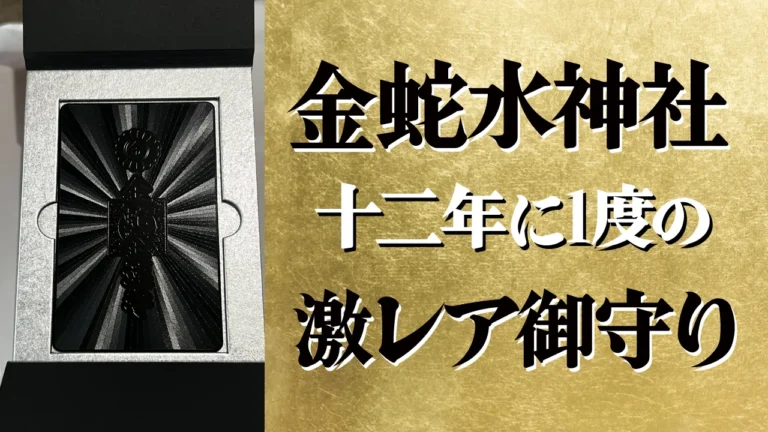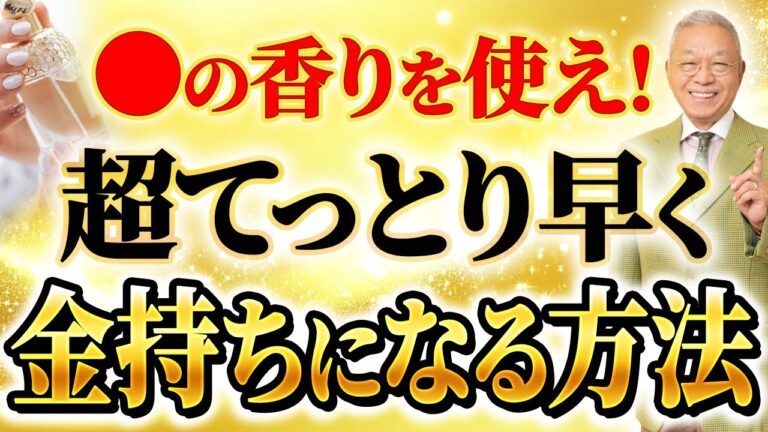青森ねぶた祭、秋田竿灯まつりと並び東北三大祭りのひとつに数えられる仙台七夕まつり。その歴史は古く、伊達政宗の時代から続く歴史あるお祭りです。豪華な装飾が商店街やアーケードに連なる壮観な姿で知られる仙台七夕まつりは、短冊に願いを書くという一般的な七夕とは異なる、金運上昇や長寿祈願といった願いをかける飾りがあるそう。
お祭りは知っていても、風習や飾りの意味など、意外に知らない仙台七夕まつりについて紹介します。
お祭りは知っていても、風習や飾りの意味など、意外に知らない仙台七夕まつりについて紹介します。
8月に行う七夕
七夕は7月7日ですが、毎年1カ月遅れの8月6~8日にかけて行われる仙台七夕まつり。その理由をはじめ、仙台七夕まつりならではの特徴から見ていきましょう!
仙台七夕まつりのはじまり
牽牛星(彦星)と織女星(織姫)が年に1度だけ逢うことを許された中国伝来の七夕は、奈良時代に日本に伝わり、江戸時代には五節句にひとつとなって全国に知れ渡ったそう。仙台でも笹と短冊に吹き流しという江戸風の七夕が取り入れられ、藩祖伊達政宗が子女の技芸上達祈願を込めて奨励したことから始まったとされています(諸説あります)。
8月に行う理由
七夕が7月7日というのは本来旧暦の話。もちろん、旧暦を用いていた江戸時代は仙台でも(当時の)7月7日に行われ、翌8日の朝に飾りを付けた笹を川に流していました。暦が変わり現在も用いる新暦になった際も、同じ7月7日に開催したのですが、後に旧暦行事を新暦の日付に合わせるために月遅れとし、8月6~8日の行事となったそうです。
七夕に七つの願い

笹に願いを込めた短冊を付けるというのは、どの地域でも変わらない七夕の姿でしょう。しかし仙台のでは短冊以外にもさまざまな飾りつけをし、それぞれに意味があるという点が他とは異なる特徴となっています。
それぞれの意味は次の通りです。
それぞれの意味は次の通りです。
短冊(たんざく)
古くは和歌を書き、学問や書道の上達を願いました。この短冊に願いを書くという風習が現在も残ったのかもしれません。
紙衣(かみごろも)
裁縫の上達を祈り、病気や災いの身代わりとして紙製の着物を捧げます。折り紙で作るときは、単色だけでなくプリント柄もおススメ。
折鶴(おりづる)
折り紙でおなじみの折鶴も、七夕飾りのひとつ。家内安全、長寿を意味し、一家の最年長者の年齢と同じ数を折った時代もあったそう。
巾着(きんちゃく)
商売繁盛、貯蓄など金運アップを願うならこれ。無駄遣いを防ぐためにも、しっかり口の閉じた巾着を作りましょう。
投網(とあみ)
魚を取る網、つまり豊漁と豊作を祈願し、食べ物に困らないように祈願するもの。幸運を集めるという意味もあります。
屑篭(くずかご)
ゴミを散らかさず、使えるものを粗末にしないという清潔と倹約の心を育む飾り。
吹き流し(ふきながし)
技芸の上達祈願に。吹き流しは、織姫の代名詞である機織り糸を垂らした様子を表現しています。くす玉とセットにして優美な飾りにしてください。
壮麗な飾りつけに彩られる仙台七夕まつりも、これらの意味を知ってから装飾を見ると、その感じ方が変わってくるはず。また、七夕に限らず、願いごとを込めた飾りを家に置いておくのもいいですね♪